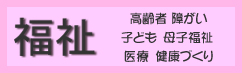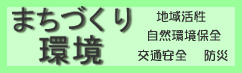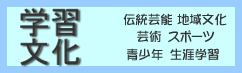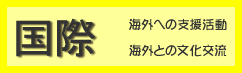助成情報
|
(タイトルをクリックすると、詳しい内容が表示されます) パルシステム茨城栃木「2024年度くらし活動助成基金」 (7月1日~7月31日消印有効)
Panasonic NPO/NGOサポートファンドforSDGs (7月16日~7月31日必着)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分野 | 貧困の解消、関連問題の解消 |
|---|---|
| 趣旨 | 本ファンドでは、SDGsの大きな目標である「貧困の解消」にむけて取り組むNPO/NGOが持続発展的に社会変革に取り組めるよう、組織課題を明らかにする組織診断や、具体的な組織課題の解決、組織運営を改善するための組織基盤強化の取り組みに助成します。 なお、昨年度から、組織基盤強化の効果がより高まるよう「組織診断からはじめるコース」の期間と助成金額を拡充するなどプログラムを改訂しています。 社会において重要な役割を果たすNPO/NGOの組織基盤強化の取り組みを通じて、市民活動の持続発展、社会課題の解決促進と新しい社会価値の創造、社会変革に貢献し、誰もが自分らしく活き活きとくらす「サステナブルな共生社会」の実現を目指してまいります。組織の自立的成長と自己変革に挑戦するNPO/NGOの皆様からの応募をお待ちしています。 |
| 内容 | 【助成対象団体】 ・海外助成:新興国・途上国など、支援を必要としている国・地域での貧困の解消、または貧困と関連のある問題の解消に向けて取り組むNGO ・国内助成:日本国内の貧困の解消、または貧困と関連のある問題の解消に向けて取り組むNPO 〇民間非営利組織であること 〇団体設立から3年以上であること ※この他、対象となる団体の要件や各分野の応募要項をご覧ください。 ※法人格の有無や種類は問いません。一般社団法人の場合は非営利型のみ。 ※財政規模1,000万円以上の団体を想定していますが、要件ではありません。 【助成対象事業】 第三者の多様で客観的な視点を取り入れた組織基盤強化の取り組みを助成対象とし、2つのコースを設けて応援します。 「組織診断からはじめるコース」 1年目に組織診断によって組織の優先課題と解決の方向性を明らかにし、組織基盤強化計画を立案および強化に取組み、2年目以降に組織課題の解決や組織運営の改善に取り組むコース。 「組織基盤強化コース」 既に組織の優先課題と解決の方向性が明らかとなっており、立案した組織基盤強化計画に基づいて、1年目から具体的な組織課題の解決や組織運営の改善に取り組むコース。 ※第三者とは、応募団体が選定するNPO/NGO支援機関やNPO/NGOの組織運営の実践者、またはNPO/NGO経営支援の専門家等を指します。 ※継続助成(2年目または3年目)については次年度の応募・選考で判断します。 |
| 期間 ・ 助成金額 |
【募集期間】 2024年7月16日(火)~7月31日(水)必着 【対象期間】 2025年1月1日~12月31日(1年間) 【助成額】 ・組織診断から始めるコース: 1団体への上限150万円(1年目) ・組織基盤強化コース: 1団体への上限200万円(毎年) ※助成総額は、「新規助成」「継続助成」あわせて、海外助成1,500万円、国内助成1,500万円。合計3,000万円 |
| 応募手続 | 【問合せ・申込み】 ・海外助成 協働事務局(認定NPO法人国際協力NGOセンター) 担当:佐藤・伊藤 〒169-0051 東京都新宿区西早稲田2-3-18 アバコビル5階 TEL: 03-5292-2911 FAX: 03-5292-2912 メール: pnsf-sdgs@janic.org ・国内助成 協働事務局(NPO法人市民社会創造ファンド) 担当:駒井・山田 〒103-0012 東京都中央区日本橋掘留町1-4-3 日本橋 MI ビル1階 TEL: 03-5623-5055 FAX: 03-5623-5057 メール: support-f@civilfund.org ・パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 企業市民活動推進部 〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷14階 メール: pnsf.sdgs@kk.jp.panasonic.com 担当:細村 |
| 関連 リンク |
Panasonic NPO/NGOサポートファンド for SDGs |
2024スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム (8月22日必着)
| 分野 | スポーツ |
|---|---|
| 趣旨 | 【趣 旨】 住友生命健康財団では、2010年に財団設立 25 周年を記念し、「スミセイ コミュニティスポーツ推進助成プログラム」を開始しました。私たちは、コミュニティスポーツを「地域において様々な人々が、楽しみながら参加・交流し、スポーツを通じて一人ひとりの健やかな暮らしの実現をめざす取り組み」と捉えています。 本プログラムでは、スポーツを楽しむ文化が地域に根づき、社会の新しい価値を創り出すような取り組みを応援します。コミュニティスポーツにかかわる全国のみなさまからのご応募をお待ちしています。 |
| 募集形式 | 【助成対象プロジェクト】 助成の対象となるプロジェクトは、【一般課題】と【特定課題】の2種類です。 【一般課題】地域の中で一人ひとりの健やかな 暮らしの実現につながるコミュニティスポーツ 【特定課題】心身の障がいや長期療養などにより社会参加が 困難な状況にある人と共に楽しめるコミュニティスポーツ ≪助成対象プロジェクトの例≫ ・地域の資源(人材、自然、施設など)を活かした取り組み ・障がい、長期療養、セクシャルマイノリティー、外国にルーツを持つ当事者や家族も共に楽しめる取り組み ・多世代がともに楽しめる取り組み ・将来世代にわたって受け継がれるようなスポーツの価値を活かした取り組み(国際的なスポーツ大会から生まれた市民活動や、地域の伝統とスポーツの融合など) ・新たな視点や工夫を取り入れるなど独自性のある取り組み *助成対象プロジェクトには、実践に必要な調査・研究、およびプロジェクトの評価やその普及・発展のための「実践研究」も含みます。但し、実践を伴なわない研究を含みません。 *応募は、1団体につき1プロジェクトとします。1団体で2プロジェクト以上応募された場合は、いずれも受付いたしません。 【助成対象となる団体】 以下の要件を満たすものとします。 ①日本国内に活動拠点のある民間の非営利団体(法人格の種類や有無を問わない)で、団体としての活動実績があること。 *団体のホームページ、SNS等で活動の様子が公開されていること。 *アドバンスコースでは原則として応募時点で2年以上の活動実績があること。 ②・団体の目的や活動が政治・宗教などに偏っておらず、反社会的勢力とは一切関わっていないこと。 *助成対象となる団体は、スポーツ分野を専門とする団体に限りません。なお、個人は対象になりません。 【助成種別】 上記の助成対象プロジェクトは、以下の取り組みの視点によって、2種に分けられます。 ①チャレンジコース: 地域におけるコミュニティスポーツのチャレンジと、その後の自立・発展をめざすもの 助成期間:2025年4月1日~2026年3月31日(1年間) 助成金額:50万以下(1年間分) 16件程度 *コミュニティスポーツのチャレンジとその自立・発展に必要な場合には連続して応募することも可能です。(2年間を上限とします) ②アドバンスコース: 地域を超えたコミュニティスポーツの展開や、特定の地域におけるコミュニティスポーツの深化をめざすもの 助成期間:2025年4月1日~2027年3月31日(2年間) 助成金額:300万円以下(2年間合計) 4件程度 *2年目の助成については、初年度の活動の進捗に問題がないこと、並びに、該当年度の当財団における予算承認が完了することが条件となります。 【助成金の使途】 プロジェクトに関わる費用であって、下記を想定していますが、必要なものはこれ以外でも可とします。 ・旅費交通費 : 交通費、宿泊費など ・謝金 : コーチ謝金、講師料など ・会議費 : 会場代、会議配布資料のコピー代など ・賃借料 : 体育施設賃借料、コート賃借料など ・機材・備品費 : スポーツ用具代(1点30万円以内) ・広報・通信費 : 広報・情報発信のための通信費、送料など ・印刷費 : チラシなどのデザイン料、印刷代など ・消耗品費 : 文具などの購入費など ・事務局人件費: プロジェクトに関わる事務局スタッフの人件費、アルバイト代など ・事務局諸経費: 事務所の光熱水費、家賃などプロジェクトに関わる部分としての按分額 |
| 応募方法 | 各応募用紙は住友生命健康財団のホームページよりダウンロードしてください。 |
| 問合先 | 【問合せ・申込み】 公益財団法人住友生命健康財団 事務局(担当:船津・福田) TEL: 03-5925-8660 / FAX: 03-3352-2021 E-mail: sports@am.sumitomolife.co.jp |
第18回かめのり大賞、かめのりさきがけ賞(8月30日必着)
| 分野 | 国際交流 |
|---|---|
| 趣旨 | 日本とアジア・オセアニア(*)の若い世代を中心とした相互理解・相互交流の促進や人材育成に草の根で貢献し、今後の活動が期待される個人または団体を顕彰します。 日本とアジア・オセアニアの若い世代の交流を通じて、未来にわたって各国との友好関係と相互理解を促進するとともに、その懸け橋となグローバル・リーダーを育成することを目的に事業を行っています。 *かめのり賞が対象とするアジア、オセアニアの国・地域 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、韓国、中国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス、台湾、香港、マカオ、オーストラリア、キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア |
| 募集形式 | 《対象個人/団体の資格》 ① 日本とアジア・オセアニアの懸け橋となる活動を目的としていること ② 過去、かめのり賞の顕彰を受けていないこと ③ HPやSNS(Instagram、Facebook、X等)にて、活動内容を公開していること *団体の法人格は問いません。個人での応募は、他薦のみとなります。 《選考基準》 次の点を総合的に評価します。 ・活動内容とこれまでの活動における貢献度、他団体との有機的な連携や協働 ・今後の活動への期待と将来の活動への可能性 ・活動内容における独自性・先駆性 ≪かめのり賞内容≫ ◇「かめのり大賞 草の根部門」では、応募団体/個人または応募団体を構成している人々(会員やボランティア)と支援先(サポートされる側)とが直接交流している活動を評価。 ◇かめのり大賞 人材育成部門」では、次の社会づくりに貢献できる人材育成を行っていることを評価。 ◇「かめのりさきがけ賞」では、他にない先駆的な取り組みを評価。*設立年数や活動期間の長さは問いません。既存事業とは別の新たな活動でも構いません。 特に次の 2 点について焦点をあてている場合は加点要素となります。 ・アジアの国、地域、人々を中心とした活動展開 ・若い世代を中心とした相互交流や人材育成の活動 ≪助成額≫ ◇かめのり大賞:「草の根部門」、「人材育成部門」の部門毎に正賞として記念の楯および副賞として100万円の活動奨励金を贈呈。 ◇かめのりさきがけ賞:正賞の記念として記念の楯および副賞として100万円の活動奨励金を贈呈 *選考の結果、選択した応募区分とは異なる区分での受賞となることもあります。 *この他、顕著な活動や実績を持つ団体/個人に「特別賞」を表彰することもあります。 *審査の結果、各賞に該当する団体/個人がない場合もあります。 *第2次(最終)選考まで進み、受賞できなかった団体/個人には30万円の活動奨励金を贈呈します。 ≪発表・表彰式≫ 発表 2024年11月下旬に審査結果を郵送にて通知 表彰式 2025年1月10日(金)に東京都内にて開催予定 *受賞者は必ず出席していただきます。 ≪活動報告書の提出≫ 2025年秋に受賞後の活動について報告書を提出していただきます。 |
| 問合先 | 《問い合わせ先・書類提出先》 〒102-0083 東京都千代田区麹町5-5 ベルヴュー麹町1F 公益財団法人かめのり財団 「かめのり賞」係 Tel: 03-3234-1694 Fax: 03-3234-1603 E-mail: info@kamenori.jp |
TOTO水環境基金 国内・海外助成団体募集(8月31日まで)
| 分 野 | 環境 |
|---|---|
| 主 旨 | TOTOグループは、水まわりを中心とした、豊かで快適な生活文化を創造することで、社会の発展に貢献し、世界の人々から信頼される企業を目指しています。持続可能な社会の実現のためには、起業の事業活動による貢献だけではなく、地域を支える団体の活動が欠かせないと考えているます。地域を支える団体と協働で社会課題の解決を目指すために、2005年度に「TOTO水環境基金」を設立し、地域の水と暮らしを関係を見直す継続的な活動を支援しています。 |
| 内 容 | ≪国内≫ 【活動内容】 地域の水環境や生物多様性の保全・再生につながる実践活動 スタートアップ・ステップアップをめざす市民団体の活動 【活動地域】 日本国内 ※過去に本基金より助成を受けた団体も応募可能ですが、同一プロジェクトに対しては最大3年間までとさせていただきます。 【助成期間】詳しくはホームページより 単年助成:2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火) 複数年助成:2025年4月1日(火)~2028年3月31日(金) 【助成金額】 単年度:上限80万円 複数年助成:上限80万円×最長3年(最大240万円)。 申請された内容を精査の上、助成金額を決定します。 ≪海外≫ 【活動内容】 各国・各エリアの水資源保全または衛生的かつ快適な生活環境づくりに向けた実践活動 【助成期間】 単年助成:2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火) 【助成金額】上限400万円 申請された内容を精査の上、助成金額を決定します。 |
| 問合せ ・ 提出先 |
TOTO株式会社 総務部 総務第一グループ 担当:川村・木村・古田 〒802-8601 北九州市小倉北区中島2-1-1 TEL:093-951-2224 / Eメール:mizukikin@jp.toto.com |
| 参考URL | TOTO水環境基金 国内・海外助成団体 |
NEW子どもたちの"こころを育む活動"表彰 (9月3日17:00応募締切)
| 分野 | 子ども |
|---|---|
| 応募できる活動 | 「こころを育む総合フォーラム」では、毎年、未来を担う子どもたちのために、全国で取り組まれている子どもたちの“こころを育む活動”を表彰しています。 子育てで大切なのは、「育てる」方法よりも、そこにいる子どもが勝手に「育つ」ような環境を用意しておくこと。そして、みんなの力を足し算にすること。「これも教育?あれも教育?」といった、ちょっと以外で自分も一枚かみたくなるような楽しい取り組みをご紹介ください。 皆さまの心温まる活動の応募をお待ちしています。 ●家庭、地域、学校、企業などのさまざまなグループで、継続している活動 ●子どもたちに持ってほしい“3つのこころ”が育まれる活動 自分に向かう“こころ” ・・・自立心や自尊心を確立し、人間らしさや自分らしさを理解するこころ 他者に向かう“こころ” ・・・人と人とのかかわりを大切にし、他者を思いやり、傷つけないこころ 社会に向かう“こころ” ・・・さまざまな価値観を尊重し、社会と自分との関係性を理解するこころ ※複数団体が合同で行っている活動、コロナ禍等の影響で休止した活動、オンラインの活動なども応募できます。また法人格の有無は問いません。 【表彰】 ●全国大賞 賞状及び賞金(50万円) ●優秀賞 賞状及び賞金(20万円) |
| 応募方法 | ●申請書: 当ホームページから「応募申請書」フォームをダウンロード |
| お問い合せ | 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-1-10 第2ローレルビル6階 公益財団法人パナソニック教育財団 TEL: 03-5521-6100 E-mail: kokoro-forum@pef.or.jp |
住友生命 第18回未来を強くする子育てプロジェクト (9月9日必着)
| 分野 | 健全育成、その他 |
|---|---|
| 趣旨 | ◆子育て支援活動の表彰趣旨: より良い子育て環境づくりに取り組む個人・団体を募集します。各地域の参考になる特徴的な子育て支援活動を社会に広く紹介し、他地域への普及を促すことで、子育て環境を整備し、子育て不安を払拭することを目的としています。 ◆女性研究者の支援趣旨: 育児のため研究の継続が困難となっている女性研究者および、育児を行いながら研究を続けている女性研究者が、研究環境や生活環境を維持・継続するための助成金を支給します。人文・社会科学分野における萌芽的な研究の発展に期待する助成です。 |
| 募集形式 | ≪子育て支援活動の表彰≫ ◆対象 より良い子育て環境づくりに資する活動を行い、成果を上げている個人・団体(規模は問いませんが、次の要件を満たすことが必要)を対象とします。 ◆要件 ①子育て支援に資する諸活動を継続的に行っていること。 ②活動内容が社会に認められ、ロールモデルとなりうるものであること。 ③活動の公表を了承していただける個人・団体であること。 ④日本国内で活動している個人・団体であること。 ⑤受賞時に、団体名・連絡先、代表者等の氏名(本名)、活動の写真、活動内容等を、新聞・雑誌、インターネット等での公表にご協力いただける方。マスコミなどからの取材にご協力いただける方。 ◆表彰: ◎内閣府特命担当大臣(こども政策)賞/表彰状 ※スミセイ未来大賞の1組に授与 ◎文部科学大臣賞/表彰状 ※スミセイ未来大賞の1組に授与 ◎スミセイ未来大賞/表彰盾、副賞100万円 ※2組程度 ◎スミセイ未来賞/表彰盾、副賞50万円 ※10組程度 ≪女性研究者への支援≫ ◆対象 現在、育児のため研究の継続が困難な女性研究者および、子育てをしながら研究を続けている女性研究者を対象とし、次の要件を満たす方の中から決定します。 ◆要件 ①人文・社会科学分野の領域で、有意義な研究テーマを持っていること。 ②原則として、応募時点で未就学児(小学校就学前の幼児)の育児を行っていること。 ③原則として、修士課程資格取得者または、博士課程在籍・資格取得者であること。 ④2名の推薦者がいること(うち1名は、所属・在籍する大学・研究所等の指導教官または所属組織の上長であることが必須)。 ⑤原則として、研究を継続していく意思のある方。 ⑥支援を受ける年度に、他の顕彰制度、助成制度で個人を対象とした研究助成を受けていないこと(科研費・育児休業給付などは受給していてもご応募いただけます)。 ⑦受賞時に、氏名(本名)やご家族との写真、研究内容等を、新聞・雑誌、インターネット等での公表にご協力いただける方。また、マスコミなどからの取材にご協力いただける方。 ※この事業では、過去の実績ではなく、子育てをしながら研究者として成長していく方を支援したいと考えています。そのため、研究内容のみで判断することはありません。 ※国籍は問いませんが、応募資料等への記載は日本語に限ります。 ◆支援:女性研究者への支援 ◎スミセイ女性研究者奨励賞 10名程度 助成金として1年間に100万円(上限)を2年間まで支給します。助成期間は2025年4月から2027年3月までの2年間の予定です。 |
| 募集 | 【募集期間】 7月8日(月)~2023年9月9日(月)必着 |
| 応募方法 | 【応募方法】 HP上から応募用紙を出力し、必要書類と一緒に郵送 |
| お問い合わせ | 「未来を強くする子育てプロジェクト」事務局W係 〒101-0065 東京都千代田区西神田2-1-6 佐藤ビル3F 電話:03-3265-2283(平日10:00~17:30) |
| 参考URL | 住友生命 「未来を強くする子育てプロジェクト」 |
宇都宮市市民交流活動推進補助金(常時募集中)
| 分野 | 国際交流・国際交流 |
|---|---|
| 趣旨 | 市内の団体の国際交流活動などに関する事業に対し、宇都宮市市民交流活動推進補助金の助成を行います。 |
| 募集形式 | 【応募条件】 (1) 申請団体が企画書に基づき、自ら企画・運営する事業であり、国際親善、国際化に寄与する内容であり、実施方法が適切で成果が期待できること。 (2) 国内においては、宇都宮市内で実施する事業であること。 (3) 日程及び事業内容が具体化していること。 (4) 政治,宗教,営利目的でないこと。 (5) 広く一般の市民の参加を募集すること。 (6) 国又は地方公共団体や公益財団法人など,他の団体から補助を受けていないこと。 【対象事業】 本市に事務所を置く団体が行う下記の事業 ・姉妹・文化友好都市との友好親善交流を目的とした事業 ・外国人住民の自立化支援、日本人との共生を目的とした事業 ・市民のための国際理解の促進及び国際協力活動に関する事業 【補助対象経費及び助成額】 ・姉妹・文化友好都市を訪問する場合及び姉妹・文化友好都市からの訪問団を受入れる場合: 通訳・翻訳料、国際親善に関する活動にかかる経費、ホストファミリーへの謝金等に直接必要な経費のうち、2分の1以内の額(上限145,000円) ・宇都宮市で姉妹・文化友好都市との友好親善を目的とした事業を実施する場合(訪問団の受入を除く):団体の事業の実施に直接必要な経費のうち、2分の1以内の額(上限50,000円) ・外国人住民の自立化支援、日本人との共生を目的とした事業:団体の事業の実施に直接必要な経費のうち、2分の1以内の額(上限50,000円) ・市民のための国際理解の促進及び国際協力活動に関する事業:団体の事業の実施に直接必要な経費のうち、2分の1以内の額(上限50,000円) |
| 期間 | 【実施期間】当該年度中(4月1日から翌3月31日まで)に実施(完了)する事業 |
| 応募方法 | ・申込様式のダウンロードは宇都宮市市民交流活動推進補助金 HP 申請様式に必要事項を記載し、国際交流プラザへ直接または送付し、提出してください。 なお、随時、受付・選考を行い、予算の上限に達した時点で締め切ります。 |
| 問合先 | 【問合せ・申込み】 宇都宮市市民まちづくり部 国際交流プラザ 〒320-0026 宇都宮市馬場通り4丁目1番1号 うつのみや表参道スクエア5階 TEL : 028-616-1567 FAX : 028-616-1568 メール: u1820@city.utsunomiya.tochigi.jp |
大竹財団助成金 (常時募集中)
| 分野 | 市民活動団体支援 |
|---|---|
| 内容・対象団体 | 【内容】 大竹財団では、主旨、活動目的を共にし、社会問題解決に取り組む個人、NGO、NPOに助成金を給付しています。 助成金を必要とされる方は、当財団の主旨や活動目的等をご理解いただいた上で、下記の提出書類を郵送にてご申請ください。 理事会にて随時審査をし、給付の可否を決定いたします。 ご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。 【対象団体】 公益、社会問題の解決に取りくむ事業をおこない、日本国内に事務所や連絡先をもつNPO、任意の市民団体、ボランティアグループ、個人 ※ 対象外となる事業、団体 ・特定の政治団体・宗教団体の活動を支援する事業(または活動履歴がある) ・営利を目的とした事業 ・国際交流を主な目的とした事業 ・学術研究・技術開発 ・学術論文の出版 ・専門家・関係者のみ出席可能なイベント ・チャリティーイベント ・高校・大学生等の学内サークル活動 ・自然共生ふれあいイベントや学習プログラム等 ・音楽イベント、アートイベントなど ・地域おこし、まちづくり等の事業 ・その他、当財団が不適切と考える事業 |
| 助成対象案件 | 【優先助成分野】 ① 平和 ② 環境/資源エネルギー ③ 人口/社会保障 ④ 国際協力 |
| 募集形態/選考方法 | 【募集形態】 公募 【選考方法】 理事会による選考 |
| 助成金額 | 上限 50万円 |
| お申し込み期間 | 通年。 年間を通じて申請を受け付けています。なお、ご申請から可否の決定に至るまでには通常1ヶ月ほどのご猶予をいただいております。 事業の開始時期を考慮し、余裕をもってご申請ください。 ※ なお、事業開始時期が直前に迫っている事業(1カ月未満)や既に始まっている事業は助成対象外ですのでご注意ください。 ゴールデンウィークや年末年始などの時期は1カ月よりもさらに余裕をもってご申請ください。 |
| お申し込み方法 | 【申込方法】 申請書とともに下記書類を添付(1,4の書類は必須。5,8は任意)の上、郵送にてご申請ください。 (郵送の際、封書おもてに「助成金申請書類在中」とご明記ください) 1.申請書 <申請書フォーム/Word形式/22.0KB> 2.申請団体(または個人)活動主旨紹介 3.申請事業の主旨説明書(事業計画書) 4.申請事業収支予算書 5.当該年度事業計画書、前年度事業報告書・決算書 6.団体の定款・寄付行為または規約 7.申請団体の意志決定機関の構成員名簿 8.その他書類(団体パンフレットや会報誌など) 【応募、審査、事業終了までの流れ】 1.申請内容のご相談 (残念ながら応募されてくる申請事業には対象外の申請が多数ございます。 当財団助成金事業として対象となりうるかどうか等、申請前に必ず電話もしくはメールで事前に事業内容をご相談ください。 事前相談なしに、書類を送られても助成申請は受理いたしません。 必ず事前にご連絡ください) 2.申請 3.一次審査(書類選考) 4.二次審査(面談) 5.助成金給付可否決定通知送付 6.助成金振込 7.事業実施 8.完了報告 9.事業完了報告書提出 10.事業評価/情報公開 |
| その他 | 【留意事項:事業の実施と事業報告について】 1.事業計画の変更について やむを得ない事由により提出した申請内容と相違が生じた場合(一部変更や遅延など)は、その旨を速やかにご連絡いただいたうえ、「事業計画変更届」を提出し、承認を受けてください。 ※「努力の末、節約できた」予算、諸事業によって支出しなかった予算など、これらについても事業計画の変更にあたります。必ずご報告をお願いします。承認を受けず事業内容を変更された場合、「助成金給付の取り消し」となりますので、必ずご連絡いただきますようご注意ください。 2.助成事業の表示について 助成事業の実施に際して、当財団から助成を受けたことがわかるよう助成表示をおこなってください。 例)本事業は、財団法人大竹財団の助成金を受けて実施しています。 3.事業終了報告書の提出 事業終了の後には速やかに事業報告書、決算報告書、または成果物等のご提出をお願いします。(1ヶ月以内を目処に) 4.助成金給付の取り消し 万一、下記の事項に該当した場合は、助成金給付の全部または一部取り消しをおこないます。 ・申請内容に不正があったと当財団が認めた場合 ・承認を受けず事業計画の全部または一部を変更したと当財団が認めた場合 ・助成金の使途変更に正当な理由がないと当財団が認めた場合 5.助成金の返還 前項の規定により「助成金給付の取り消し」を受けた場合、指定の期日までに助成金の全部または一部の返還を求めます。 |
| 申請先/お問合せ | 〒104-0031 東京都中央区京橋1-1-5セントラルビル11F 財団法人大竹財団(事務局/担当:関盛) Tel 03-3272-3900 Fax 03-3274-1707 |
| 参考URL | 財団法人 大竹財団 助成金 http://ohdake-foundation.org/index.php/grant |
助成情報は団体のホームページや募集要項を参照し、
まちぴあ事務局で入力しているものです。
詳細は関連URLのリンクより当該団体のサイトにてご確認ください。
|
分類別ページ
|
|---|